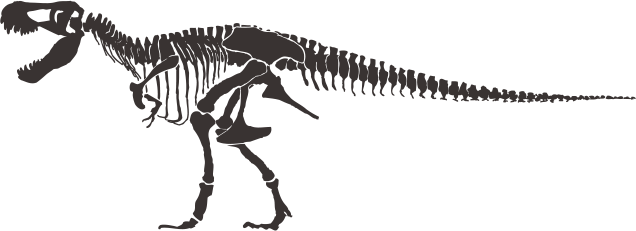棟方志功が
訪れた窯元
令和元年10月12日(土)〜12月1日(日)にいのちのたび博物館で開催された、「九州発!棟方志功の旅 掘り起こされた足跡と交流」。
今回は特別展に合わせて、棟方志功が訪れた3つの窯元を訪ねました。

髙取焼・髙取八仙窯
14代受け継がれる、伝統と新しさを両立する窯元
初めに訪れたのは、14代目まで続く長い歴史を持った髙取八仙窯さん。14代目髙取忍さんに髙取焼について解説していただきました。
髙取八仙窯について
髙取八仙窯さんは1600年から黒田藩の御用窯として茶道具を作り続けている窯元です。中でも一番愛用されているものは茶器になります。
また、茶器の他にも私たちが普段使うような器も作っており、同じ窯で両方を作っているのは日本でもここだけだそうです。

▼茶入を持つスタッフ
髙取焼について
髙取焼の特徴は、驚くほどの薄さと軽さ。
ここまで薄くて軽いものは日本でもここにしかない、とのことです。
髙取八仙窯さんでは「唐物写し」という名品の写しの茶入の他にも、様々な種類の器を作られています。

▼茶入の底面。底の糸切りの目が交点より少し右でないと名品の写しにはなりません。

▼左は日本で生まれた碗形という形。底が茶筅に合わせて広がっています。
右は大陸より渡来した杉形という形。
棟方志功と髙取八仙窯について

▼左が戦国武将で茶人であった古田織部が愛用した形。全体的に歪んでいます。右が古田織部の弟子、小堀遠州が愛用した形。戦国時代が終わり、形も歪んだものから一か所だけ押した「前押せ(まえおせ)」が特徴です。
棟方志功さんが髙取八仙窯さんの元に訪ねられたのは、13代目の髙取八仙さんが40歳ごろの時です。
棟方志功さんと実際にお会いした髙取八仙さんに、当時の様子をお聞きしました。
-棟方志功さんについて教えてください
棟方志功さんは奥さんと見えられ、2晩ほど滞在されました。
(八仙さんが)40歳ごろのときではっきりとは覚えてないけれど、秋口だった。
普通の人というかんじで、特別な感じはしませんでした。
「目が悪いのによく描けますね」と言ったら、「筆が動いているから自分は手を添えるだけ」と言われていましたね。
-来られた後で変化はありましたか?
特に変化はなかったです。
色紙とかも、「描いてたらキリがなくて疲れるから出さないでくれ」と言われて貰いませんでした。
-棟方志功さんは青森の出身ですが、方言などはなかったですか?
方言とかもなかったです。普通の方でしたよ。

▼13代目 髙取八仙さん
-八仙さんはどのような気持ちで焼物を作られていますか?
安川電機の社員であり、北九州や福岡県の文化保護委員なども務めた美和弥之助さんから、
「頭で考えて小手先で作るな」と言われました。
そこが難しい。考えて作ると固さと冷たさが、考えないものは柔らかさや自然さがあります。
そこに至ることが出来るかは、未知です。
-髙取焼の将来についてどのようにお考えですか?
「その話は娘に…」
ここで、14代目の娘さんの由布子さんが登場!
13代目に変わって、由布子さんがお話してくれました。
-改めて、将来についてお聞かせください。
アートが好きで、東京の美術大学で産業デザインを学んだ後、改めて家業に注目しました。
髙取焼の技法を面白く伝えたいと思っています。
また、大量生産されたものよりも、一つずつ違うものを作りたい。そうして好きなものを選んでもらうほうが、大切に長く愛用してもらえます。
そういうモノづくりがしたいです。
そのために、従来の髙取焼の釉薬の掛け方ではなく、様々な組み合わせを実験しています。
-伝統的ではない髙取焼を作ることに、反対されませんでしたか?
特に反対されることなく、自由に作っています。
家族からは「八仙窯の冒険係」と呼ばれるほどです。
父(14代目髙取忍さん)も遊び心のある髙取焼を作っていますよ。

▼「手作りのものを、お客さんが喜んで買ってくれることに喜びを感じる」 と語る由布子さん。

▼左から、14代目髙取忍さん、髙取由布子さん、13代目髙取八仙さん
髙取八仙窯さんでは、焼き物の文化を尊重し、
ご家族で伝統と自由な考え方を組み合わせた髙取焼を作っていることがインタビューを通して伝わりました。

上野焼・髙鶴華山窯
今では貴重!薪で焼くここだわり
髙取八仙窯さんの次にインタビューをさせていただいたのは、上野焼・髙鶴華山窯さんです。
上野焼について
上野焼は、1602年に細川忠興に取り立てられた喜蔵高国が、上野の窯で焼物を始めたのが由来です。
髙鶴華山窯さんは1938年から上野焼を作られています。

▼ずらりと並ぶ焼物は圧巻!
髙鶴華山窯と上野焼の特徴
上野焼の特徴は釉薬の多種多様さです。
上野焼の代表的なものは青流しですが、今はほとんど総青を焼いているそうです。
時代の変化に合わせて釉薬の掛け方や技法を変えていきました。
また、現在では灯油やガスで焼く窯が多い中、髙鶴華山窯さんでは薪で20時間以上かけて焼いているものもあります。
薪で焼いたものは時間をかけるためしっかりしており、底が焼けて味が出るそうです。
薪で焼くものは今ではあまり見ることもないため貴重です。

▼中央が青流し、右が総青
棟方志功と髙鶴華山窯について
-棟方志功さんについて教えてください
今から65年前(昭和29年)に来られました。
私はあっていませんが、兄がお会いしました。
この辺りのスケッチを行っていたそうです。
祖父が志功さんにカニの箸置きをプレゼントしたと聞いています。

▼取材風景。暑い中、笑顔で取材に応じてもらいました。
上野焼には様々な種類やデザインがあるので、手が滑らないとか、手触りや感覚でお気に入りのものを見つけてください。
髙鶴華山窯
TEL : 0947-28-8021
〒 822-1102 福岡県田川郡福智町上野皿山1884


豊前吉右衛門窯
刻って染める 華やかで美しい刻染付
最後に訪れたのは、豊前吉右衛門窯さんです。
豊前吉右衛門窯について
豊前吉右衛門窯さんは1949年にはじまり、現在は2代目の永末修策さんが伝統を受け継いでいます。
豊前吉右衛門さんの品物のほとんどには模様がついており、中にはペルシャ風と言われる人もいるそうです。
豊前吉右衛門窯の特徴
豊前吉右衛門窯さんは、伝統ある「刻染付(ほりそめつけ)」を行っています。
「刻染付」は、半乾きの素地に墨で下絵を描きをし、鉄筆様の道具で文様を刻(ほ)ります。
乾燥・素焼き後に刻った溝に顔料を入れて彩色をしていきます。
豊前吉右衛門窯さんで作られる焼物には、美しい文様が刻られているのが特徴です。
なかなか大変な作業なので、刻染付をする窯は少ないそうです。

▼文様が刻られた状態

▼左が焼いたもので右が焼く前。焼くと少し縮みます。

▼電気ろくろを使用し、製作を行っています。

▼手前が施釉し焼いたものです。青瓷(せいじ)と呼ばれます。

▼かつては登り窯だったが、時間がかかる、ずっと見ていないといけない、様々な薪を用意しないといけない…ということでガス窯を使用されています。
棟方志功と豊前吉右衛門窯について
-棟方志功さんについて教えてください
会ったのは4~5歳のときだったので…
強烈な印象なのは覚えています。
上野の山越えをして来られ、絵付けやスケッチを行っていました。

▼取材の様子。筆者の後ろにはずらりと焼き物が並んでいました。
陶芸の楽しみは、陶芸教室で作る楽しみ、料理に合わせて選ぶ楽しみなど人それぞれ。
お酒が好きな人はぐい呑みをよく買われたり、自分のライフスタイルに合わせて焼物を楽しめます。
数ある焼物の中からどのように選べばいいのか尋ねると、
「値段の高い低いではなく、第一印象で、自分の判断で選んでください」とのことです。